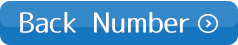つくば市研究学園、下妻市、八千代、筑西明野で小中学生・高校生の学力伸ばすなら学習塾のBES塾へ。


私たちが普段使っている日本語を調べてみると、いろいろと奥深いものがあります。
今回は助数詞についての話になります。
助数詞とは、いわゆるものを数える際の単位です。
本なら1冊、紙なら1枚、といった具合です。
外国人が日本語を学ぶときに、この助数詞の扱いや種類の多さについては苦労するそうです。
日本語では助数詞の種類がおよそ500種類と非常に多いです。
日常的に使用するものはもっと少ないですが、それでも数十種類の助数詞を使い分けているそうです。
日本語が助数詞の種類で世界一なのかどうかは定かではないそうですが、中国や韓国でも助数詞は数十種類だそうで、世界的に見てもトップクラスに多いことは間違いないと思われます。
そんな助数詞においても面白い雑学があります。
有名なところでいうと、ウサギの数え方ですね。
「1匹」と数えることもできますが、「1羽」と数えることもあります。
鳥でもないのに、どうして1羽と数えるのでしょうか。
これは昔、殺生を禁じられた仏教徒がウサギの肉を食べる時に、「これは鳥の肉だから食べても問題無い」と言い訳をしたことが由来となっています。
他にも、馬は「1頭」と数えるほかに「1匹」とも数えるようですが、これも面白い由来があります。
馬を背後から見た時に、お尻が二つに割れている見た目から匹と数えるようなのです。
そう言われると、「匹」という漢字の見た目がお尻のようにも見えますね。
実際、「匹」という漢字の成り立ちの一説には、馬の尻の見た目から作られたという説があるようです。
日常的に使っている日本語もいろいろと調べてみると、面白い話や興味深い話があります。
学校の授業だけでなく、こういった雑学について調べてみるといい気分転換になるかもしれませんね。